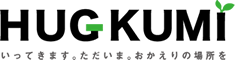住宅ローン控除と諸費用ローン:賢くお得にマイホームを手に入れる方法
マイホーム購入は人生の一大イベント。住宅ローンを組むだけでなく、諸費用についても賢く計画することが、理想の住まいを手に入れるための重要なポイントです。

目次
住宅ローン控除の基本を理解する
住宅ローン控除の基本的な仕組み、控除額の計算方法、および控除を受けるための条件について解説します。これは、住宅購入者が税制優遇を最大限に活用し、初期費用を抑えるための第一歩となります。
住宅ローン控除とは?仕組みを解説
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、または増改築等を行った場合に、一定期間、年末のローン残高に応じて所得税から税金が控除される制度です。これは、住宅取得を促進し、国民の居住環境の向上を図るための国の税制優遇措置の一つです。具体的には、年末時点での住宅ローン残高の一定割合が、その年の所得税額から直接差し引かれます。これにより、納税者は実質的な税負担の軽減を受けることができます。
控除額の計算方法と控除を受けるための条件
住宅ローン控除の控除額は、原則として、年末の住宅ローン残高の0.7%(※令和4年以降の入居者の場合)を上限として計算されます。ただし、控除額には上限額が設定されており、住宅の種類や入居年によって異なります。例えば、認定住宅や省エネ基準に適合する住宅など、特定の要件を満たす住宅では、より高い控除限度額が適用される場合があります。控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、控除を受ける年の12月31日までに入居していること、床面積が50平方メートル以上であること、取得した住宅を自身が居住するために使用すること、そして、合計所得金額が2,000万円以下であることなどが主な条件として挙げられます。また、親族等から購入・建築した住宅は対象外となる場合が多いです。
住宅ローン控除の対象となる費用、ならない費用
住宅ローン控除の対象となる費用とならない費用を明確に区別し、読者の疑問を解消します。具体的な費用項目を一覧で示し、対象外となる理由も説明することで、誤解を防ぎ、正確な知識を提供します。

住宅ローン控除の対象となる費用とならない費用
| 費用項目 | 対象となるか | 備考 |
|---|---|---|
| 建物本体の購入費用 | 対象 | 住宅ローン控除の基本的な対象 |
| 土地の購入費用 | 対象 | 建物と同時に取得した場合 |
| 増改築、リフォーム費用 | 対象 | 一定の要件を満たす場合 |
| 印紙税(建物・土地購入時) | 対象 | |
| 登録免許税 | 対象 | |
| 不動産取得税 | 対象 | 取得の翌年分の所得税から控除 |
| ローン契約書印紙税 | 対象 | |
| 住宅ローン本体の年末残高 | 対象 | 控除額の計算根拠 |
| 家具・家電購入費用 | 対象外 | |
| 引越し費用 | 対象外 | |
| 登記費用(司法書士報酬など) | 対象外 | |
| 火災保険料、地震保険料 | 対象外 | |
| 保証料 | 対象外 | |
| 仲介手数料 | 対象外 | |
| ローン手数料(事務手数料) | 対象外 | |
| 繰上返済手数料 | 対象外 | |
| 建物の取得に直接関係のない費用 | 対象外 |
住宅ローン控除の対象とならない費用
住宅ローン控除の対象とならない、諸費用ローンや一時的な手数料など、具体的な費用項目と対象外となる理由を解説します。
- 諸費用ローン : 家具・家電の購入費用、引越し費用、登記費用(司法書士報酬など)、火災保険料、地震保険料、保証料、仲介手数料、ローン手数料(事務手数料)、繰上返済手数料など。これらは住宅ローン控除の対象となる「住宅の取得等」に直接かかる費用ではないため、対象外となります。
- 建物の取得に直接関係のない費用 : 例えば、住宅ローンの保証料や、火災保険料、リフォームにかかる費用でも、住宅ローン控除の対象となる工事とは直接関係のないものは対象外となる場合があります。
諸費用ローンとは?メリット・デメリット
住宅購入には、物件価格以外にも登記費用、仲介手数料、印紙税、ローン保証料、火災保険料など、様々な「諸費用」がかかります。これらの諸費用を賄うために利用できるのが「諸費用ローン」です。諸費用ローンは、住宅ローンとは別に用意される場合や、住宅ローンに含めて借り入れられる場合があります。

諸費用ローンの種類と特徴
諸費用ローンには、主に以下の2つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
- 住宅ローンに諸費用を含めて借り入れるケース : 多くの金融機関では、住宅ローンの借入額に諸費用を含めて申し込むことが可能です。この方法のメリットは、別途ローンを組む手間が省けること、そして住宅ローンと同じ金利が適用されるため、金利負担を抑えられる可能性があることです。ただし、借入額が増えるため、月々の返済額や総返済額が増加する点に注意が必要です。また、諸費用分まで含めて住宅ローン控除の対象となるか、事前に金融機関や税務署に確認しておくと良いでしょう。
- 諸費用ローンを別途利用するケース : 住宅ローンとは別に、諸費用のみを対象としたローン商品が用意されている場合があります。こちらは、住宅ローンとは異なる金利が設定されることが多く、住宅ローンに含めるよりも金利が高めに設定されているケースが見られます。メリットとしては、住宅ローンの借入額を抑えられるため、月々の返済負担を軽減できる可能性があります。また、住宅ローン控除の対象額を諸費用分と明確に分けたい場合に有効です。金利や手数料、返済条件などをしっかり比較検討し、最も有利な選択肢を見つけることが大切です。
諸費用ローンのメリット
諸費用ローンを活用することで、住宅購入における初期費用の負担を軽減し、スムーズな購入プロセスを実現できるというメリットがあります。
- 一時的な資金負担の軽減 : 住宅購入時には、物件価格以外にも諸費用として数十万円から数百万円のまとまった資金が必要となります。自己資金で全額を賄えない場合でも、諸費用ローンを利用することで、手元の資金を温存しつつ、住宅購入を進めることが可能になります。これにより、急な出費への備えや、その他の生活資金を確保しながら、住宅購入の夢を実現しやすくなります。
- 住宅購入の初期費用を抑えられる : 諸費用ローンを住宅ローンに含めず、別途借り入れることで、住宅ローンの借入額自体を低く抑えることができます。住宅ローン控除は、年末のローン残高に対して適用されるため、諸費用分を切り離すことで、住宅ローン控除の対象となる金額を最大化できる可能性があります(ただし、控除額には上限があります)。また、諸費用ローンが住宅ローンより低金利で提供される場合(稀ですが)、総返済額を抑えられる可能性もあります。
諸費用ローンのデメリット
諸費用ローンを利用する際には、いくつかの注意点やデメリットが存在します。これらを理解せずに利用すると、後々後悔する可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。
- 金利の上乗せや負担の増加 : 諸費用ローンは、住宅ローンとは別に設定されることが多く、住宅ローンよりも金利が高めに設定されている場合があります。住宅ローンに諸費用を含めて借り入れる場合でも、借入額が増えるため、住宅ローン自体の金利負担が増加します。結果として、総返済額が増加し、月々の返済負担が重くなる可能性があります。
- 返済負担の増加 : 諸費用ローンを別途利用した場合、住宅ローンの返済とは別に、諸費用ローンの返済も行う必要があります。これにより、毎月の支出が増加し、家計への負担が大きくなる可能性があります。特に、諸費用ローンが長期の返済期間を持つ場合、長期にわたって返済負担が続くことになります。
- 住宅ローン控除との兼ね合い : 諸費用ローンを住宅ローンに含めて借り入れた場合、その全額が住宅ローン控除の対象となるわけではありません。住宅ローン控除の対象となるのは、原則として購入した家屋や土地の取得対価(またはそれに付随する費用)であり、諸費用ローンで賄った金額が控除対象となるかは、個別のケースや税制によって異なります。諸費用ローンを別途利用した場合、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン残高を、諸費用ローン分と明確に分ける必要があります。税務申告の際に、これらの区分を正確に行うことが重要です。
諸費用ローンの金利と選び方
諸費用ローンの金利相場を把握し、読者が自分に合ったローンを効果的に選ぶためのポイントを解説します。金利だけでなく、手数料や返済条件なども含めて比較検討できるよう、具体的な情報を提供します。

諸費用ローンの金利相場
現在、諸費用ローンで一般的に見られる金利の相場は、金融機関や時期によって変動しますが、おおよそ年1%台後半から3%台程度が中心となっています。住宅ローン本体の金利に上乗せする形や、別途専用のローン商品として提供される場合があります。 金利タイプとしては、主に「変動金利」と「固定金利」の二つがあります。変動金利は、市場金利の動向によって半年ごとなどに金利が見直されるため、当初の金利は低めに設定される傾向がありますが、将来的に金利が上昇するリスクを伴います。
一方、固定金利は、契約期間中の金利が一定であるため、将来の金利変動リスクを避けたい場合に適していますが、一般的に変動金利よりも当初の金利は高めに設定されることが多いです。 また、諸費用ローン専用の商品の中には、住宅ローン本体とは異なる金利体系が適用される場合もありますので、比較検討する際には、適用される金利タイプと現在の金利水準をしっかりと確認することが重要です。
諸費用ローンの選び方のポイント
金利だけでなく、保証料、手数料、返済期間、繰り上げ返済の条件など、諸費用ローンを選ぶ際に考慮すべき重要なポイントを解説します。
- 保証料 : ローンを利用する際に連帯保証人や保証会社を利用する場合に発生する費用です。金融機関によっては、保証料が無料の場合や、一括払い・分割払い、または金利に上乗せするタイプなど、支払い方法が異なります。保証料の有無や金額によって、実質的な負担額が変わるため、総支払額を比較する上で重要な要素となります。
- 手数料 : 諸費用ローンには、契約事務手数料、印紙代、保証会社手数料、繰り上げ返済手数料など、様々な手数料が発生することがあります。これらの手数料は、ローン商品や金融機関によって金額が大きく異なるため、契約前に必ず確認し、総支払額に含めてシミュレーションすることが大切です。特に、借入額に対して手数料の割合が高い場合は、他の金融機関と比較検討する価値があります。
- 返済期間 : ローンの返済が完了するまでの期間を指します。返済期間が長いほど、毎月の返済額は軽減されますが、その反面、支払う利息の総額は増加する傾向にあります。ご自身の収入やライフプランに合わせて、無理のない返済計画を立てられる期間を設定することが重要です。
- 繰り上げ返済の条件 : 予定よりも多くの金額を返済することで、ローン残高を減らし、支払う利息を軽減する制度です。繰り上げ返済を行う際に、手数料がかかるのか、また、いくらから繰り上げ返済が可能か(最低金額)、といった条件を確認しておきましょう。手数料無料で柔軟に繰り上げ返済ができるローンは、将来的に総支払額を抑えたい場合に有利です。
諸費用を抑えるための節約術
住宅購入には、物件価格以外にも登記費用、印紙税、仲介手数料、火災保険料、ローン手数料など、様々な諸費用がかかります。これらの諸費用をいかに抑えるかが、初期費用を賢く節約するための鍵となります。

各種手数料の比較検討
住宅購入で発生する諸費用は多岐にわたりますが、それぞれに比較検討して節約できるポイントがあります。
- 登記費用 : 司法書士に依頼する際の報酬は、事務所によって異なる場合があります。複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。
- 印紙税 : 住宅ローン控除の対象となる場合、印紙税額が軽減されることがあります。契約書の内容をよく確認しましょう。
- 仲介手数料: 不動産仲介業者に支払う手数料です。仲介手数料の上限は法律で定められていますが、交渉次第で割引が可能な場合もあります。特に、売主と買主の両方から手数料を受け取る「両手仲介」か、一方のみから受け取る「片手仲介」かによって、業者のスタンスが変わることもあります。
- 火災保険料 : 火災保険は、保険会社や補償内容によって保険料が大きく異なります。住宅ローンを組む際に金融機関が指定する最低限の補償内容を満たしつつ、複数の保険会社の商品を比較検討し、最適なプランを選びましょう。長期契約やインターネット割引などを利用するのも効果的です。
- ローン手数料 : 金融機関やローン商品によって、事務手数料や保証料が異なります。金利だけでなく、これらの諸費用も含めて総支払額で比較することが大切です。
税金対策:固定資産税と不動産取得税
住宅購入時には、不動産取得税や購入後に毎年課される固定資産税といった税金が発生します。これらの税金についても、利用できる軽減措置や控除制度を理解しておくことで、大幅な節税につながる可能性があります。
まず、不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に一度だけ課される税金です。新築住宅や一定の要件を満たす増改築を行った場合、税額が軽減される特例措置があります。例えば、住宅の床面積が一定基準以下であれば、税額から一定額が控除されます。この特例措置を受けるためには、原則として、取得した日から6ヶ月以内に都道府県税事務所に申告が必要です。
次に、固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に対して課される地方税です。新築住宅については、一定の要件を満たす場合に、建築後一定期間、税額が2分の1に減額される特例措置があります。この減額期間は、木造住宅などの一般住宅では3年間、耐火建築住宅などでは5年間です。また、土地についても、住宅用地として利用されている土地(小規模住宅用地など)には、税負担を軽減するための特例措置が設けられています。これらの特例措置は自動的に適用される場合もありますが、適用要件や期間を確認し、必要に応じて自治体に確認することが重要です。
まとめ:賢く利用して、理想の住まいを手に入れよう
本記事では、住宅ローン控除を最大限に活用し、諸費用ローンを賢く利用し、さらには諸費用を節約するための実践的な方法を解説しました。これらの知識を統合することで、読者の皆様は住宅購入にかかる費用全体を最適化し、経済的な負担を軽減しながら、理想の住まいを安心して手に入れることが可能になります。住宅ローン控除を最大限に受け、諸費用を含めた資金計画をしっかりと立てることで、夢のマイホーム実現への道がより確かなものとなるでしょう。
投稿者プロフィール

- 経営コンサルティング事業部部長・ブランディングマネージャー
-
「お前は、建築業には絶対に進むな...」建設業の厳しさを知り尽くした父から贈られた言葉。けれど、苦労している父親の背中や、「きつい・汚い・危険」と言われる過酷な職場環境で歯を食いしばり懸命に働く家族や職人さんたちの姿が忘れられず「この業界を変えたい」と志し、コンサルティング業界の道に進み10年。豊富な実績を誇り全国の地域No.1工務店からの熱狂的なファンが多く、これまで建築業界にはなかった発想や唯一無二のアイデアで差別化を図り「ゼロからイチをつくる」ブランディングのプロ。2030年には新築着工棟数が半減する未来を見据えるなかで、業界全体の活性化のためにブランディングや生産性向上のノウハウを分かち合う「競争ではなく、共創」の考えを創造し、新たな建築業界の世界観をつくる”先駆者”。
武田純吾のプロフィール詳細を見る
最新の投稿
 移住2025.12.22地方移住で叶える!ワークライフバランスと地方創生への貢献
移住2025.12.22地方移住で叶える!ワークライフバランスと地方創生への貢献 移住2025.12.15郊外暮らしの夢、新幹線通勤で叶える!費用・快適さ・注意点まとめ
移住2025.12.15郊外暮らしの夢、新幹線通勤で叶える!費用・快適さ・注意点まとめ リノベーション2025.12.08中古住宅リノベで最大〇〇万円お得に!2024年最新の補助金と減税制度
リノベーション2025.12.08中古住宅リノベで最大〇〇万円お得に!2024年最新の補助金と減税制度 リノベーション2025.12.04リフォーム?リノベーション?失敗しないための完全ガイド:費用、業者選び、注意点
リノベーション2025.12.04リフォーム?リノベーション?失敗しないための完全ガイド:費用、業者選び、注意点